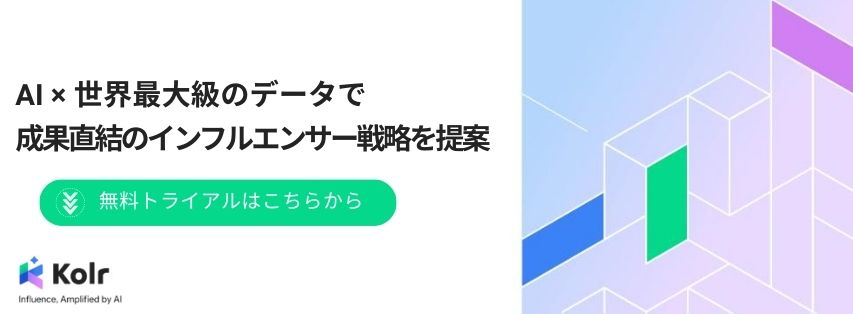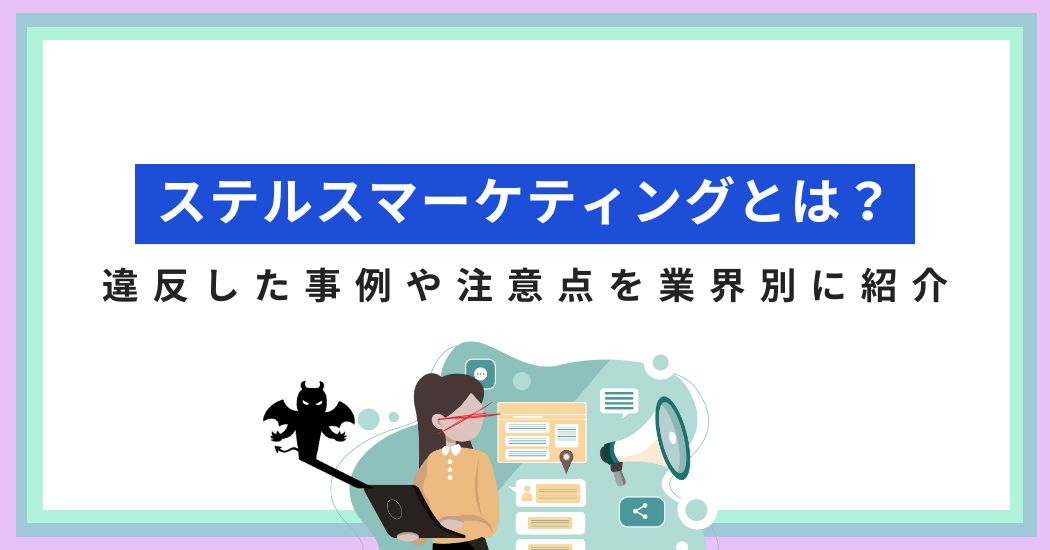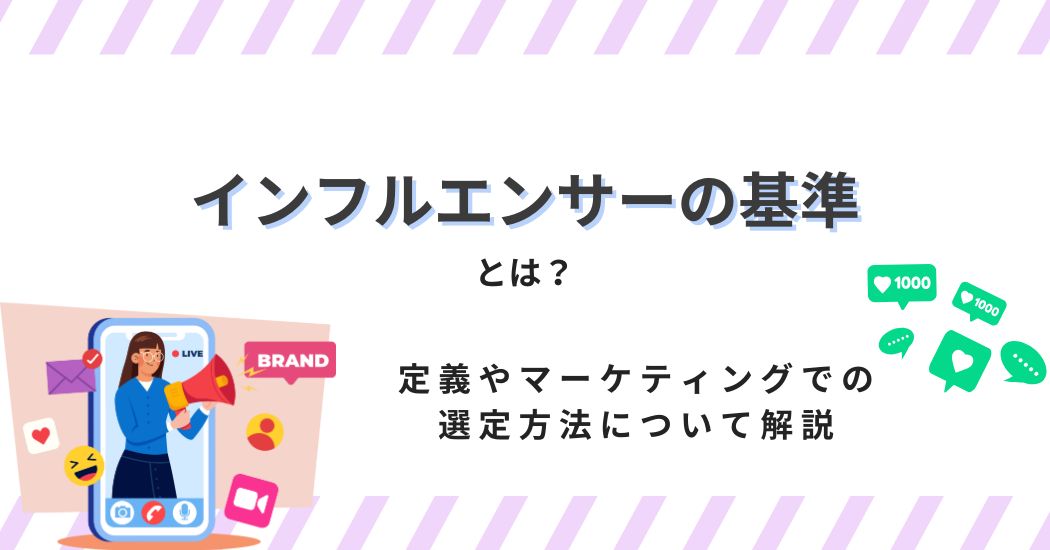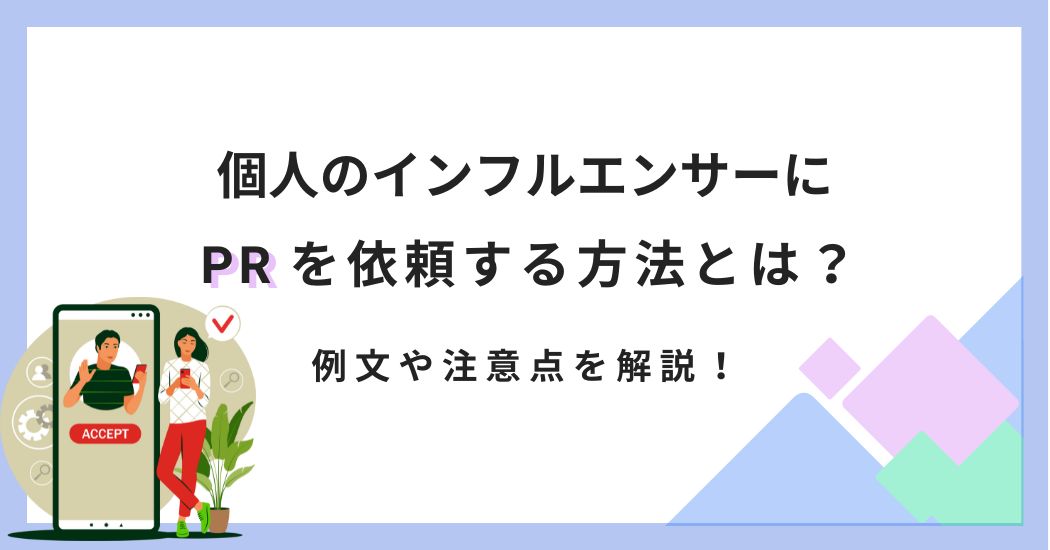「ステルスマーケティングとは?」
「ステルスマーケティング規制の違反事例とは?」
という疑問をお持ちではありませんか?
本記事では、そんな疑問の解決に役立つ内容を
- ステルスマーケティングの基礎知識
- ステルスマーケティングの業界別の事例
- ステルスマーケティングの注意点
の順に解説します。
インフルエンサーマーケティングの実施を検討している方に役立つ記事です。
ぜひ最後までご覧ください。
ステルスマーケティングとは?

最近は「ステルスマーケティング規制」「ステマ違反」といった言葉をよく見かけるようになりました。
消費者庁のホームページでは、ステルスマーケティング(Stealth Marketing)は「広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すこと」と定義されています。
広告であることが明確であれば、消費者は情報にある程度の誇張・誇大が含まれていると認識することが可能です。
しかし、ステルスマーケティングの場合、広告である事実がわかりづらく、消費者が正しい判断をできなくなってしまいます。
ステルスマーケティングの種類
ステルスマーケティングは大きく「なりすまし型」と「利益提供型」に分けられます。
以下でそれぞれについて確認していきましょう。
なりすまし型
なりすまし型とは、企業が第三者を装って、自社商品・サービスに関する情報発信を行うことです。
「サクラ」や「やらせ」と言われることもあります。
例えば、Googleマップの口コミ投稿において、従業員であることを偽り顧客としてのレビューを投稿する行為は、なりすまし型のステルスマーケティングです。
利益提供型
利益提供型とは、芸能人やインフルエンサーなどに報酬を支払っているにも関わらず、広告であることを隠して、自社に有利な情報を発信してもらうことです。
例えば、化粧品会社が美容系インフルエンサーに報酬を支払い、自社製品にとって有益な情報を発信してもらう行為は、利益提供型のステルスマーケティングに該当します。
ステマ規制とは?
ステルスマーケティング規制(以下、ステマ規制)とは、令和5年10月1日から開始された景品表示法による規制のことです。
一般消費者が広告であることが判断できない表示は、ステマ規制違反と見なされます。
なお、ここで言う表示とは「消費者に対して、商品・サービスを知らせる広告や表示全般」のことで、チラシや新聞、テレビCMなどのほか、SNS投稿や口コミも含まれます。
ステマ規制の詳細情報については、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:ステマ規制はいつから?行政処分の対象となる違反事例をわかりやすく解説
【業界別】ステルスマーケティングの事例

それでは、どのような表示がステルスマーケティングに該当するのでしょうか?
以下で、業界別にステルスマーケティングの事例を確認していきましょう。
事例1:美容業界
始めに紹介する事例は、化粧品会社の美容系インフルエンサーを活用した事例です。
ある化粧品会社に勤めるインフルエンサーが、第三者であることを装って、自社製品を高く評価した投稿を複数回行いました。
特定の化粧品会社の商品を何回も紹介していることから、ステルスマーケティング規制への違反が疑われました。
調査の結果、インフルエンサーが化粧品会社の社員であることが発覚し、化粧品会社による謝罪が行われました。
事例2:アニメ業界
世界的に大ヒットを記録したアニメ映画で、ステルスマーケティング規制違反が報告された事例です。
映画公開後、7名の漫画家やイラストレーターが映画を賞賛するコンテンツをSNSにアップロードしました。
ほぼ同じタイミングで投稿されていたことや、同じハッシュタグが使用されていたことで、ステルスマーケティングであることが疑われました。
結果的に、報酬が支払われたマーケティングであることが発覚し、提供元の会社が謝罪文を発表しました。
事例3:EC業界
続いて紹介する事例は、ECサイトにおける不正レビューの事例です。
あるECサイトを運営する企業がインフルエンサーではない一般消費者に対して報酬を支払い、高評価のレビューを投稿させました。
商品を購入していないユーザーからのレビューも含まれ、ステルスマーケティング規制に違反すると判断されました。
他にも、競合に大量の低評価をつけさせる不正レビューも横行しており、問題視されています。
事例4:小売業界
最後に紹介する事例は、小売りチェーンを展開する企業の事例です。
自社ブランドのイメージを向上するため、あるPR会社に依頼しました。
そのPR会社は一般人カップルの旅行ブログを立ち上げ、小売りチェーンに肯定的な投稿を行いました。
消費者団体が一般人カップルが雇われていることや、旅行費がPR会社によって支払われていたことが発覚し、PR会社のCEOによる謝罪が行われました。
ステルスマーケティングの注意点

それでは、ステルスマーケティング規制に違反しないためにはどうすればいいのでしょうか?
以下で、ステルスマーケティングの注意点を解説します。
SNSではステルスマーケティングが発生しやすい
まず、SNSではステルスマーケティングが発生しやすいことに留意しましょう。
例えば、InstagramやX、TikTokなどのSNSが挙げられます。
SNSは情報を拡散させやすく、ユーザー数も多いです。
リアルタイムに広く情報を拡散できるため、不正業者によってもよく使われます。
SNSにおけるステルスマーケティング規制に違反しないためにも、タイアップ投稿ラベルを使用する、PR表記を行うなどの対策を行いましょう。
過去の投稿も規制対象となる
ステルスマーケティングで注意したいポイントは、過去の投稿も規制対象となる点です。
ステルスマーケティング規制が始まったのは令和5年10月1日ですが、それ以前に投稿されたコンテンツへの対応も必要になります(施行後も継続して表示されている場合)。
消費者庁のホームページ(Q&Aのうち「Q20」の部分)にもその旨が記載されているので、確認してみてください。
参考:消費者庁「ステルスマーケティングに関するQ&A」
インフルエンサーマーケティングの規制対象となるケースを理解する
インフルエンサーマーケティングの施策によっては、ステルスマーケティングの規制対象となるケースがあります。
具体例として、以下が挙げられるでしょう。
- インフルエンサーに無償でギフティングを行い、商品を賞賛する内容を投稿するように指示した場合
- 会社Aで働くインフルエンサーが自身の正体を隠し、会社Aの商品を紹介した場合
- 企業がインフルエンサーにレビューを依頼したが、投稿にPR表記がない場合
他にも、報酬や企業とインフルエンサーのやり取り、事業者の意思の介入などによって、ステルスマーケティングの規制対象となるため注意が必要です。
専門会社のサポートを利用するのがおすすめ
インフルエンサーマーケティングを初めて行う企業や、社内に専門知識・ノウハウが不足している企業は、専門会社のサポートを利用すると良いでしょう。
マーケティング業務を効率化できるだけでなく、ステルスマーケティングなどの法規制にも対応できるようになります。
iKala Japanは世界最大級のインフルエンサーデータとAIを駆使した戦略的なインフルエンサーマーケティングを提供するプラットフォーム「Kolr(カラー)」を運営しています。
インフルエンサーマーケティングに関する疑問や質問がございましたら、お気軽にご相談ください。
まとめ

今回の記事では、ステルスマーケティングの基礎知識、ステルスマーケティングに該当する事例、注意点などについて解説しました。
インフルエンサーに依頼した投稿がステルスマーケティングに該当すると見なされた場合、行政処分を受けることになります。
企業の信頼性が損なわれるリスクがあるため、ステルスマーケティング規制への慎重な対応が必要です。
iKala Japanは、インフルエンサーマーケティングの専門知識やノウハウを備えています。
また、Kolr(カラー)では、AIによるインフルエンサーの提案や競合他社の分析など、成果に密着したインフルエンサー施策のためのサポートを提供しています。
ぜひ無料トライアルから、お試しください。